
商品のコンセプトを踏まえて試作づくりです

発表会、ミーティングでの本郷鶏肉様のフィードバックを踏まえてチーム内で検討してきたものをまずは報告します
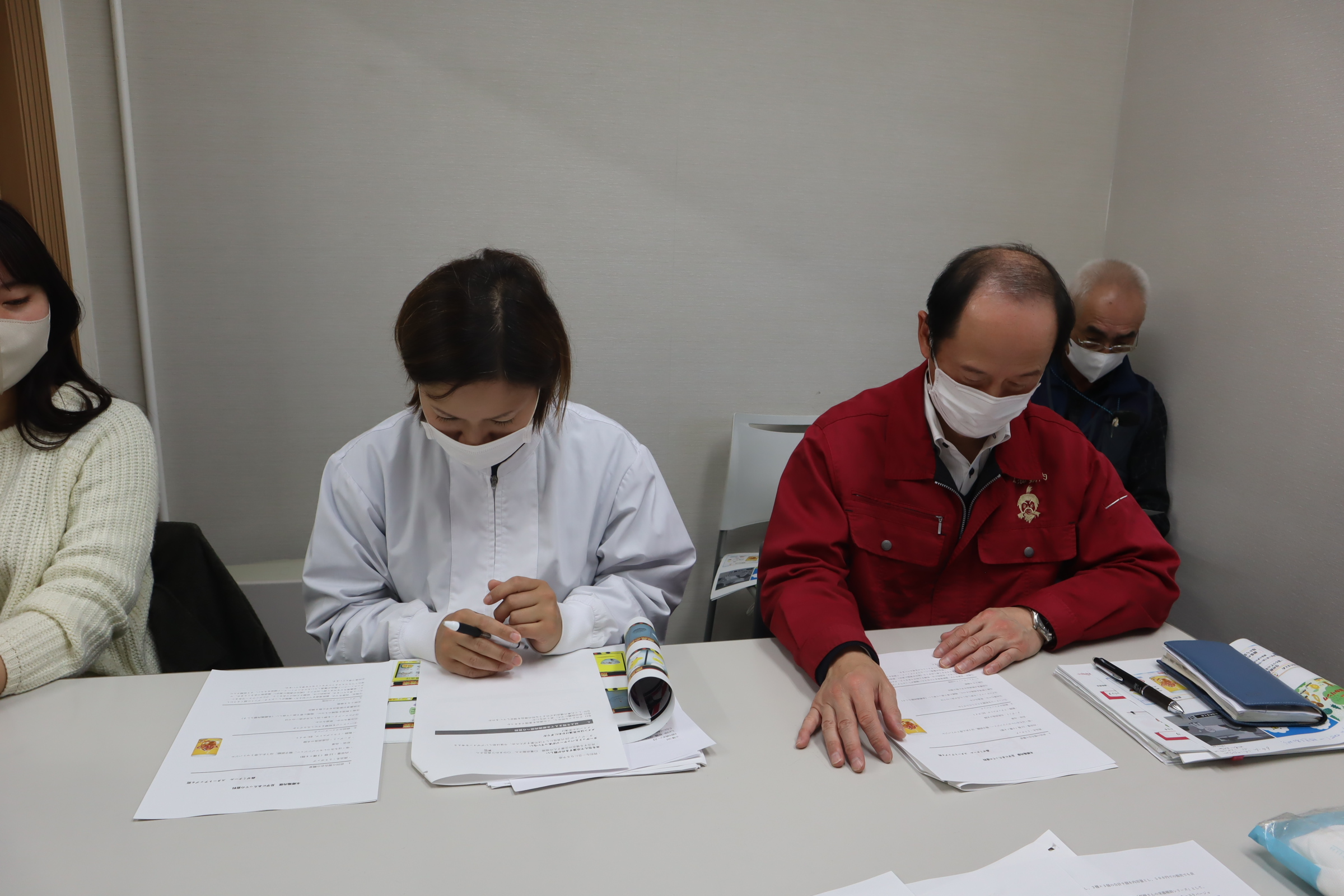
それをお聞きいただき、改めてフィードバックをいただきます

森ゼミの他の班が試作した内容も紹介をいただきました

コンセプトを踏まえ容量・分量などを意識しながら試作づくりです

イメージをもとに具材を切ったり、調理したり

試作をつくる上でも森ゼミ生と本郷鶏肉様の協働作業です

作業の時間や、工程なども意識しながら試作づくりをおこない
企業情報学部の森ゼミナールでは、「企業イノベーションプロジェクト」と題して、スタートアッププロジェクト、理論研究、実践研究をもとに、地域企業を中心とした成熟企業の問題解決活動(コンセプトおよび商品・サービスの開発)に取り組んでいます。
2024年度は、プロジェクトのスタートアッププロジェクトとして、本郷鶏肉様(長野県松本市)と協働し、同社の今後の方向性の検討や新商品の企画・開発を中心としたプロジェクトを進めることになりました。4月に2024年度の森ゼミが始動し、ゼミを6つのグループに編成し、この問題解決活動がはじまりました。
同社は、独自な調理技術・製造技術・調味料開発技術をもとに、松本市・塩尻市のソウルフードの山賊焼を中核の商品とし、ミートデリカ商品、中華、チルド、地活のさまざまな商品を展開されています。ここまで森ゼミ生は、企業様との懇談会、企業様への中間発表会、企業様との商品開発などにかかるミーティングを実施してきました。
このミーティングにおける同社よりいただいたフィードバックをもとに、チームごとに商品案を再検討し、この度、共同での商品開発に向けて森ゼミ第2班も試作づくりを進めることになりました。第2班が考案したものは、朝起きるのが楽しみなる朝食を意識した「おに茶漬け」(おにぎりでも、お茶漬けでも)という商品です
訪問日
2024年11月21日
訪問先
有限会社本郷鶏肉(松本市)
訪問先で対応いただいた方
取締役会長 山﨑様、代表取締役社長 平野様、商品開発責任者 高木様、管理部 田島様
訪問したメンバー
森ゼミ生(鈴木昇斗、馬屋原美涼、望月七菜、丸山裕土)
提案報告の概要
問事項は、以下の通りです。
1)おにぎりの「米」と「包む」という点に懸念がある現状だが、どのような形であればこの商品を実現できそうか。
2)前回お話していただいた「丼」とはどのようなものを想像されており、案として出してくださった背景があればお聞きしたい。
3)しぐれ煮の場合はどのような形の商品を想定しているのか。
これらの質問に対して、それぞれ下記のようにご回答をいただきました。
1)お米は顧客自身に用意してもらうなど、中身の部分のみを販売する形であれば実現可能性が高い。
2)かつて山賊焼きまぶし丼やとり天、かつまぶし丼を販売したことがあり、そのノウハウを活かすことにより新商品の実現がより近いものになる。
3)商品の想定というよりかは、しぐれ煮のようなものであれば作ることが可能であるとのこと。
同社と共同で試作づくりを行い、森ゼミ生の感想と今後の展望は、以下の通りです。
所感と今後の展開・展望
〈所感〉
グラム数に関して、想像していた量と施策をしてみて実際に必要となる量ではかなりギャップがあった。また、一つの商品を作っていくその工程にどれほどの準備と段階があるのかを実感したと同時に、その面白みを感じた。一回の試作の中でも、試行錯誤しながら最も理想とする味・食感に近づけていくことに楽しさと達成感を感じた。これから実際に商品化するとなったときには、何度も試作を重ねることにより厳密でより理想に近いものを作っていけるようにしたい。そのために、自分たちが形にしたい商品というものをより具体的に、しっかりとイメージしておく必要があると感じた。
〈今後の展開〉
・本郷鶏肉様から、冷凍でない形のお米を使った商品は様々な要因で難しいとのお話があったため、そのお話を踏まえながら自分たちのこれまでの商品案を活かした商品案を再検討する必要がある。
・形を変えたとしても、これまで同様お茶漬けの方向性で行くとしたとき、その具材のグラム数の考え直しが必要。朝ごはんとして適切な内容量である必要性に加え、ターゲットとする人々の朝ご飯の量・朝の時間をよりイメージして具現化していく必要がある。
・価格想定(原価計算を含む)
・再検討案の施策づくり
・顧客に届き、口にしてもらい、その後の気持ちの変化といったような、この商品によって生み出されるシチュエーションの想定
【以上、森ゼミスタートアップ2班のまとめより】

いよいよ完成です!

試作したものを実食します

完成したものを平野社長にお茶漬けにする作業をしていただきました

試作を実食し、コメントをしあいながら課題を探ります。
森ゼミ2班では、この試作づくりをもとに、商品のブラッシュアップを進め、商品の中身、コンセプト、販売予測・市場性予測、マーケティングの展開などについてさらに検討し、同社と共同による商品開発を進めていきたいと考えています。

商品化に向けてとても有意義な機会となりました
関連リンク
教員紹介
教授 / 学部長
森 俊也
モリ シュンヤ
所属
企業情報学部、地域経営学部
