県立長野図書館などとの連携による講座開催
これからの地域の学びでは、地域資料を収集するだけでなく、テキスト・画像・映像などの多様なデジタル資源を収集もしくは地域の人々と共に創成することが求められます。その共有のための「ネット上の本棚」が「デジタルコモンズ(デジタルな共有地)」です。デジタル知識基盤化の時代を迎え、各地域・学校・図書館・博物館・行政などでデータのデジタル化を計画・実践できるデジタルアーキビストの養成が急務となっています。本講座は、長野県内の各地域の知識・データを共有できる情報のプラットフォーム「信州デジタルコモンズ」の創成を目指し、県立長野図書館などとの連携により実施するものです。

デジタルアーキビスト養成講座の実施風景
信州デジタルコモンズの創成に長野大学の研究を活かす
「信州デジタルコモンズ」は信州各地域に根差した「それぞれの地域学」の資料や学習成果を集成する「未来のデジタル化された図書館」です。専門家か一般の人かを問わず、各地域の誰もが地域の知識の源泉となるデータや教材を生産・蓄積できるようにすることが課題です。加えて社会の知識基盤化が進行しつつあるこの先、地域の知の在りようはどう変わるのか、図書館や博物館などはどう変わるのか、そうした社会の変革・変化に対して大学はそれにどう貢献できるのか、そうした知の方向付けがこれまで以上に求められる時代となりました。そのため、長野大学の企業情報学部における「メディア環境学」(前川道博教授)、環境ツーリズム学部における「信州学」(市川正夫教授)、それぞれの研究と研究実績を活かした学際的な社会貢献プログラムとすべく「信州デジタルコモンズ」プロジェクトを立ち上げました。本講座はその起点とするものです。第1回「信州学ビフォーアフター」7/1実施
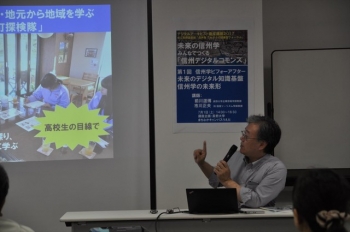
講義「未来のデジタル知識基盤」
長野大学企業情報学部 前川道博教授

講義「信州学の未来形」
長野大学環境ツーリズム学部 市川正夫教授
第2回「知識基盤施設のビフォーアフター」7/17実施

知識資源の宝庫「公文書館」
信濃史学会会長 小松芳郎氏
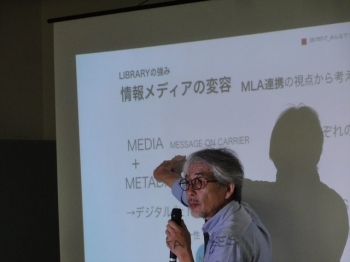
未来の図書館はこうなる
県立長野図書館館長 平賀研也氏
地域のデジタルコモンズとは
研究者・学習者の個別の成果物(ポートフォリオ)を蓄積し公開して行くこと、知識形成に役立つ関連の資料・データの品揃えを増やして行くこと、これらの包摂・横断、さらにそれらの相互関係を可視化する情報の網目の組成(関連性のリンク付け)を行っていけるメディア環境が「デジタルコモンズ」です。デジタルコモンズは、一人一人から見ると自分のポートフォリオや地域資料を蓄積・共有できる「私の本棚」です。それらはコモンズに乗っていることにより、誰もが見合い、共有できるものとなります。このようにデジタルコモンズは、信州学の学(知識)と学び(学習プロセス)の知識やデータを載せ合える言わば「ネット上の本棚」となります。
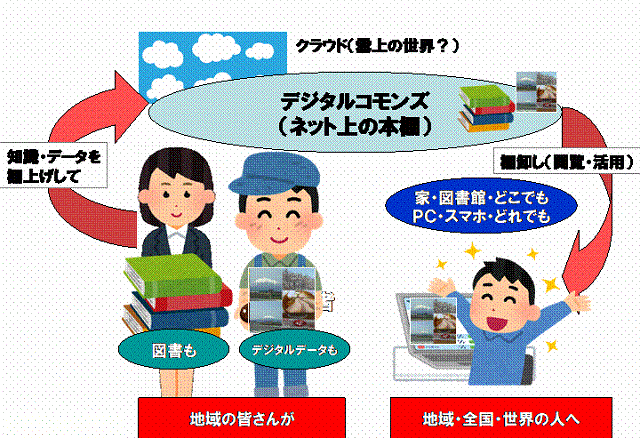
デジタルコモンズは未来の図書館
大学周辺からだけでなく全県、他県からも受講
本講座は7~9月、計5回実施します。デジタル化の進展は否応なしに私たちの社会環境を大きく変えつつあります。MLA(M博物館・L図書館・A公文書館)に代表される地域の知識基盤施設には資料のデジタルアーカイブ化、またネットを介したサービスなどの対応が求められています。大学や学校(小中高校)においては地域社会と連結して学びを実践するデジタル化の支援による地域とのより密接な学びの実践が求められてきています。こうした社会ニーズを背景に、本講座は長野大学の地元・上田市周辺からだけでなく、長野県全域、県外からも幅広く受講されています。社会全体では知識・データのデジタルアーカイブ化、デジタル資源を活用した地域学習などの取り組みは立ち遅た状況にあります。本講座は、こうした社会変革のニーズに応えるものです。本講座の受講者は延べ50名を超えました。受講者それぞれが今後各地域の知の拠点となるMLAの諸施設、学校などでのデジタルアーカイブの活用への期待を担っています。信州(長野県)全域に自律分散的に立ち上がりつつある/これから立ち上がろうとしているデジタルアーカイブを緩やかに連携させることにより、全県的な知のプラットフォーム「信州デジタルコモンズ」創成の試みをここから始動させます。