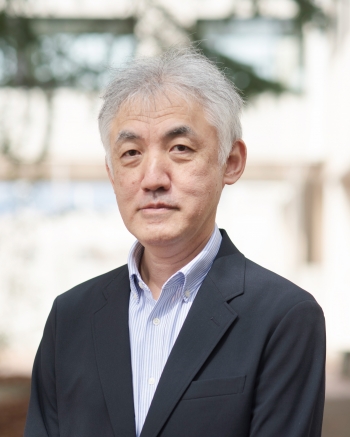
教授
松下 重雄
マツシタ シゲオ
所属 |
環境ツーリズム学部、地域経営学部 |
|---|---|
学位 |
博士(工学) |
研究テーマ |
地方都市・農村におけるコミュニティ再生、地域協働型まちづくり方策/まちづくり組織運営 |
研究 |
コミュニティ・デザイン、地域協働、持続可能な暮らし、住民主体の観光まちづくり、まちづくりNPO、社会的企業、都市計画、農村計画 |
研究詳細 |
ゼミナール内容
「地域協働のまちづくり」×「持続可能な暮らし」
「地域協働のまちづくり」×「持続可能な暮らし」をテーマに進めるゼミでのグループ研究活動は、地域関係者との協働活動によって取り組むことが基本です。とくに、地域で活動する多様なまちづくりNPOや住民組織と連携して実施します。そのため、研究手法は、地域課題の解決に向けて地域とともに実践的に取り組む、いわゆるアクション・リサーチ的手法を採用します。フィールドワークが多いことが特徴です。 また、こうした活動を支えるために、文献講読などのゼミ全体での演習、グループ研究と連動した個人研究活動をおこなっています。
研究内容
地方都市・農村におけるコミュニティ再生に関する研究
古民家再生をとおした子どもの居場所づくりやコミュニティ・ビジネスのあり方、地域の空き資源を活用したコミュニティ拠点形成、住民主体の観光まちづくり/エコツーリズムの展開方策に関する研究を実践的におこなっています。
地域協働型まちづくり方策/まちづくり組織運営に関する研究
英国のパートナーシップ型のまちづくり方策であるGroundworkを基軸に、地域協働型(中間支援型)のまちづくり組織や社会的企業のあり方について研究をおこなっています。近年では、台湾やインドなどでサステイナブルな地域づくりを志向する取り組みに注目しています。
地域協働型教育
まちづくりの現場実践から学ぶ
まちづくりの主体は地域にあります。学生がまちづくりのプロセスに触媒役として関わりながら、システム思考を身につけるとともに、地域社会に貢献することを目指しています。
高校生へのメッセージ
ちょっと反抗しないとマズいかも
「これでいいのだ。」ですんだのが、ぼくら昭和世代の価値観です。ところが、気候変動や人口減少時代を迎え、いままでの社会システムに限界が見えてきました。にも関わらず、そのレジームを現世代は壊すことができません。その一方で現代の若者の多くは、大人たちの作ったスマホ社会にまんまと没入させられ、思考を停められています。そのうちに歪みが臨界点に達して、社会や環境の秩序が崩壊し、気がついたらAIに支配されているかもしれません。世の中のしくみや価値観は、人々の営みによって築かれてきました。だけど、サステイナブルの社会への新たな変革は、新しい世代によるイノベーションによってのみ達成されます。だからボーッとしてないで、ちょっと焦って抗って、立ち上がってほしいと思います。